これまで行ってきたワークショップや実践の紹介です(2015/9 更新)
これまで実施してきた多くのワークショップ実践についてまとめました。なるべくカテゴリごとにまとめるようにしています。カテゴリに入らないものは新しい順に上に並べています。
■2014年3月〜2015年9月
- 立教大学経営学部BUSINESS LEADERSHIP PROGRAM(BLP)に関する情報まとめ
- 立教大学経営学部教職員向けワークショップ
- 立教大学経営学部教員・SA合宿
- 立教リーダーシップカンファレンス2015での登壇
- 「授業作りの舞台裏」に関する動画が公開
- リーダーシップ開発学ワークショップ(大学生研究フォーラム@京都大学)
- 高校教員を対象とした「インタラクティブな教え方」に関する研修
■「食・農・健康の未来」に関するワークショップを実施しました(2014年2・3月)
このワークショップはつくばグローバル・イノベーション推進機構による「つくばにおける新たな研究開発テーマの発掘・企画のための仕組みの構築」プロジェクトで、内閣府の国際戦略総合特区事業の一環で行われました。三菱総研とIBLCが事務局となり、安斎勇樹さんとともに企画・実施を行いました。
■「教え方」に関する研修をおこないました(2014年3月)
某社にて、「ワークショップのファシリテーション」のやり方に関する研修をおこないました。どのようにファシリテーションするのか、何を気をつけるべきかについて体験を通して学ぶ活動を実施しました。
■「地域と医療」について考えるLEGOワークショップを実施してきました
2013年9月16日に、一般社団法人Medical Studioさんから依頼を受けて「地域と医療」をテーマにしたワークショップを実施してきました。詳細はこちらのブログ記事をご覧下さい。
https://www.tate-lab.net/mt/2013/09/lego-medical.html
■【研究会】説得するのは「社外」でなく「社内」?:イノベーションの鍵となる「社内説得」の理論と実践を学ぶ
2013年9月18日に「説得するのは「社外」でなく「社内」?:イノベーションの鍵となる「社内説得」の理論と実践を学ぶ」という研究会を実施しました。詳細は以下の記事をご覧下さい。
https://www.tate-lab.net/mt/2013/09/post-293.html
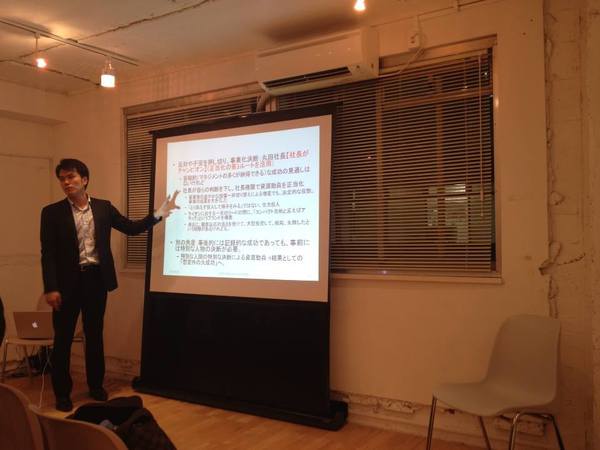
■ソーシャル・ランチの会を開催しています
2013年の4月から本郷キャンパスにてランチをしながら交流するランチ会を実施しています。詳細は以下をご覧下さい。
https://www.tate-lab.net/mt/2013/09/post-291.html
■対話を生み出す実践知をトップランナーから学ぶ
2013年7月6日に「対話をうみだす”実践知”を、トップランナーから学ぶ」を実施しました。
【速報版報告】「対話をうみだす”実践知”を、トップランナーから学ぶ」、本日無事終了いたしました!
http://www.nakahara-lab.net/blog/2013/07/post_2045.html
■ ライティング・ワークショップ
大学生・大学院生を対象に、大学における学び方に関する講座を実施しています。レポートの書き方に関するもの、研究の進め方に関するものなどを、体験を通じて学べるような講座を実施しています。
・ 東京学芸大学の授業外講座「学芸カフェテリア」にて「レポートの書き方講座」を実施(2012/5/9)
・ 東京学芸大学の授業外講座「学芸カフェテリア」にて「卒論の書き方に関する講座」を実施(2012/11/12)
・ 大学生・大学院生を対象に「先行研究の読み方・まとめ方講座」を実施。実施場所は、青山学院大学(2011/11/5,2012/6/24)、千葉大学(2011/11/21)、東京大学(2011/12/13)など。
■キャリア・ワークショップ
大学生を対象に、自分の大学生活を振りかえるワークショップを実施しています。このワークショップでは、自分の大学生活をグラフに表現し、他者に語ることで、自らのキャリアを振り返ってもらうことを目的としています。
実践内容は以下の書籍にまとめました。
舘野泰一(2012)第9章 大学教育とワークショップ 佐伯胖 ・苅宿俊文・高木光太郎(編) まなび学ワークショップ第2巻,pp197-219, 東京大学出版会
?・2013年5月23日実施
「30代後半のキャリアを考える:激流、筏下りの「先」にあるもの」
FUJITSUユニバーシティ・山口由美子さん・安達優彦さんをお招きして
http://www.nakahara-lab.net/blog/2013/04/30_4.html
■ ワークショップ・デザイン講座
日本生産性本部様からのご依頼で、企業の人事部の方を対象に「ワークショップ・デザイン」に関する講座を実施しました(2012/2/10)。この講座では、ワークショップに関する理論やデザインの方法について、体験を通じて学ぶものでした。
■研究室マネジメントに関するケースメソッド教材の開発・ワークショップの実施
大学教員・大学院生を対象に、研究室マネジメントについて考えるケースメソッド教材の開発をし、ワークショップを行いました。実践の成果は学会にて発表を行っています。実践は、鳥取大学、日本教育工学会のワークショップ、研究室マネジメントに関するフォーラムなどで行いました。
岡本絵莉,舘野泰一,宮野公樹,可知直芳,山本祐輔(2011)研究室内コミュニケーションに関するケーススタディ教材の開発と実践.日本教育工学会第27回全国大会講演論文集,pp.537- 538 : 首都大学東京
■越境学習に関する研究会
社外で学ぶビジネスパーソンの学びである「越境学習」について、講師を行ったり、研究会を行っています。以下の書籍の内容に関するものです。
舘野泰一(2012) 職場を越境するビジネスパーソンに関する研究:社外の勉強会に参加しているビジネスパーソンはどのような人なのか,中原淳(編),職場学習の探究 企業人の成長を考える実証研究,pp281-312,生産性出版
「越境学習」×「イノベーション論」組織を超えたイノベーションの可能性を考えよう!
http://business-research-lab.com/report-03/index.html
社外で学ぶビジネスパーソンの実態「越境学習」
http://hrdm.jp/2012/04/post-109.html
越境学習と新たな「キャリア」に関する研究会(2012/5/22)
http://www.nakahara-lab.net/blog/2012/04/academic_hack_-.html
■学びのサードプレイスについて考える研究会(サードプレイスコレクション2010)の企画・実施

2010年1月23日に六本木superdeluxe(スーパーデラックス)で、「学びのサードプレイス」の可能性を考える「サードプレイスコレクション2010」というイベントを自らが中心になり開催しました。このイベントでは、家庭でも職場でもない第三の場を「対話・創造・学びの場」として捉え、企業や学校などで行われているさまざまな実践について考えました。約200名が参加しました。。
イベントの内容は「知がめぐり、人がつながる場のデザイン―働く大人が学び続ける”ラーニングバー”というしくみ」(英治出版)にも一部紹介されています。
サードプレイスコレクション2010の取材記事が掲載されました!
https://www.tate-lab.net/mt/2010/02/2010-3.html
「サードプレイスコレクション2010」が終わった!
http://bit.ly/aoq12S
・登壇者一覧(敬称略)
苅宿俊文(青山学院大学)、美馬のゆり(公立はこだて未来大学)、熊倉敬聡(慶應義塾大学) 、長岡健(法政大学) 、中原淳(東京大学)、飯田美樹(カフェ文化研究家) 、森玲奈(東京大学)、黒崎輝男(流石創造集団株式会社)、鈴木菜央(株式会社ビオピオ/greenz.jp)、遠藤幹子(office mikiko 一級建築士事務所)、中村繁(株式会社リクルートエージェント)、安斎利洋(システムアーティスト)、中村理恵子(アーティスト)
イベントの様子は以下の動画をご覧下さい。
■おとなの女性のためのサイエンスイベント
おとなの女性が食事をしたり、実験をすることでサイエンスについて学べる「ScienceGirls’Talk」というイベントを実施しました。詳細は以下のサイトをご覧下さい。
- ScienceGirlsTalk(https://www.facebook.com/ScienceGirlsTalk)
■「プチ学会」の実施
領域にとらわれない人のつながりをもとにした学会を開く「プチ学会」というイベントを実施しています。詳細は以下のサイトを参照。
- Unlaboratory(https://www.facebook.com/Unlaboratory)
■PARTYstream for JAPANの企画・実施
2011年6月18日にチャリティ・カフェイベント「PARTYstream for JAPAN」を実施しました。このイベントでは、「働き方・経営 × アート × 教育 × 科学コミュニケーション ポスト311、何が変わるか、変わらぬか、変えたいか」をテーマに、ゲストを招いて議論を行いました。
ゲスト一覧
・慶應義塾大学 高橋俊介さん【働き方・経営】
・Tokyo Art Beat【アート】
・NPO法人カタリバ 今村久美さん【教育】
・日本科学未来館 池辺靖さん【科学コミュニケーション】
イベントの詳細はこちらをご覧下さい。
http://partystream.jp/?p=436
■組織学習・組織人材の最先端の話題をあつかう研究者と実務家のための研究会(Learning bar)の企画・実施への参加
中原淳(東京大学大学総合教育研究センター准教授)の実施する公開研究会(通称Learning barラーニングバー)の企画・実施に関わりました。この研究会は、「企業・組織の人材育成」「企業HRD」「組織学習」をテーマに、のべ2000人が参加しました。
私はこの研究会の活動の一部をデザインしたり、Learning barのスピンオフ企画である「Learning bar-X」の企画などに関わりました。
Learning barの説明については以下の動画をご覧下さい。
・2009/3/27 カフェ研究会 場づくりのサイエンスとアートをめざして
→プログラムの一部を担当
中原先生のblog:カフェ研究会が終わった!: 場づくりのサイエンスとアートをめざして
http://bit.ly/cH9L2x
ワークショップ部のWeb:カフェ研究会での発表が終わりました!
http://bit.ly/8ZzqO4
・2009/7/29 Learning bar-X インプロと学びを考える
→全体の場作り、プログラムの作成、当日の司会を担当
[インプロ]「Learning bar-X インプロと学びを考える」終了!
http://bit.ly/c59RT9
・2009/10/24「 Learning barのつくりかた」についてインタビュー
→メルマガとして配信しました
もしよろしければ、こちらをどうぞ!
「Learning barのつくりかた」のメールマガジン
http://bit.ly/3Zx22N
・2009/10/30 ワークプレイスラーニング2009後のパーティー
→メンター役として、企画のサポート、当日の準備やお手伝いをしました
「茶道に学ぶ、大人の学び」パーティレポート
http://bit.ly/9XotvH
・2009/12/4 組織理念を共有するとは!?:三井物産渡辺さん×神戸大学金井先生
→サードプレイスコレクション2010についてプレゼン
Learning bar 「組織理念を共有するとは!?:三井物産渡辺さん×神戸大学金井先生」にて
http://www.nakahara-lab.net/blog/2009/12/learning_bar_28.html
■ 実践を行っているコミュニティ
ワークショップやイベントは以下のコミュニティを自らが主催することで実施しています。
- ワークショップ部(http://utworkshop.jimdo.com/)
- Unlaboratory(https://www.facebook.com/Unlaboratory)
- ScienceGirlsTalk(https://www.facebook.com/ScienceGirlsTalk)
■メールマガジン執筆
1.Beating「5分でわかる学習理論講座」の執筆
東京大学大学院 情報学環 ベネッセ先端教育技術学講座「BEAT」のメールマガジン「Beating」のを執筆していました。第14号から第21号までを担当していました。
学習を「個人の営み」ではなく、「社会的な営み」として捉え直す〜「社会的構成主義」http://www.beatiii.jp/beating/014.html
学びあいを行う集団〜「実践共同体」
http://www.beatiii.jp/beating/015.html
実践を通した学習のなかで知識を獲得する〜「認知的徒弟制」
http://www.beatiii.jp/beating/016.html
他人との学び合いを通して、自立した学習者を育成する〜「相互教授法」
http://www.beatiii.jp/beating/017.html
知識が集まる。それはパズルのように。〜「ジグソーメソッド」
http://www.beatiii.jp/beating/018.html
あなたの心をひきとめる。それは「アンカードインストラクション」
http://www.beatiii.jp/beating/019.html
ゴールを目指して突っ走れ!知識は自然とついてくる!〜「ゴールベースドシナリオ」
http://www.beatiii.jp/beating/020.html
「体験=経験」じゃない!反省して初めて「経験」なんだ!〜「問題解決学習」
http://www.beatiii.jp/beating/021.html
■e-Learning配信スタッフ
東京大学大学院学際情報学府の講義をインターネット上で受講できるサイト「iiionline」のスタッフをしています。授業の撮影、アップロードを行っています。
http://iiionline.iii.u-tokyo.ac.jp/









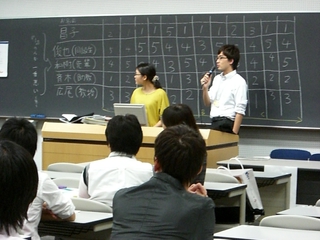







コメントを残す